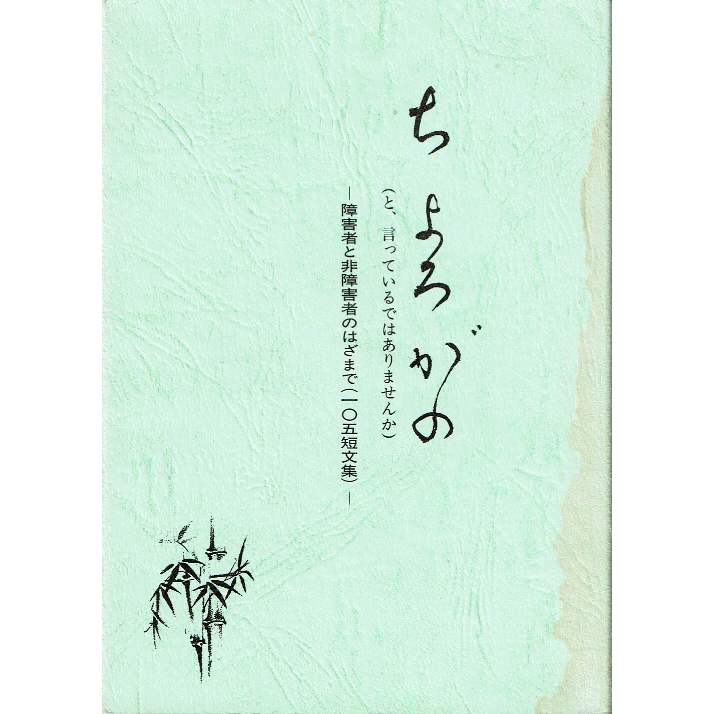姉の家に寄宿していた頃、何か夫婦でもめていた翌日、厳しい顔の姉が急に私をどこか「障害者能力判定とそれに応じた職業紹介」をするような施設に連れて行った。
しかし、障害者としての当時の私の能力では「残念ながら、紹介できる職業はない」と係員から言われたときの暗然とした姉の表情を忘れられない。帰りの車中の会話はどうしても途切れがちだった。
その後数年が経ち、強引に姉の家を出ることを決意した私は、残された能力の一つ、ピンセットを口にくわえて小さな活字を組んで端物印刷を始めた。基礎的知識のない当初は、大いに苦労したが、爾来五〇年続けて来て、二人の子どもを成長させ、年とった親を無事に見送ることができた。もちろんそれまでには、母、妻、さらには子どもたちの絶え間ない協力があったのはいうまでもないが、ともかくいつもその中心にいて、さまざまな思いと力を尽くしてきた。現在は息子に教えられたパソコン製版による会報や文集などの制作に励んでいるが、かえりみて、あのときの機能判定の係員には、唇にピンセットをくわえてする仕事は想像外であったに違いない。そんな想像外の仕事を私にできるようにさせたもの、それこそ、信仰による希望と思う。