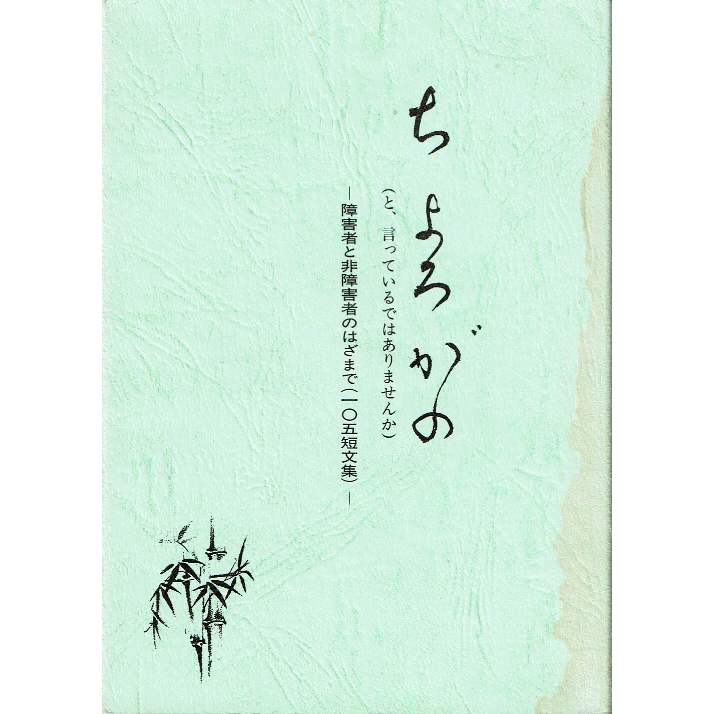私には六歳年上の姉がいた。私たち姉弟はみな中国・青島の生まれで、学校は居留民団がつくった日本人学校に通っていた(ようだ。後で聞いたのだが、その学校の校長さんに中村八大さんのお父さんがおられたそうだ)。その姉が小学校一年生のとき学校からハシカをもらってきた。姉自身はすぐ治ったのだが、妹の出産で母が入院中の留守に私にそのハシカをうつしてしまった。ちょうど満一歳の誕生日を迎えたばかりの私のために、母はわざわざ日本人の子守さんを雇ったのに、かかりつけの医者にも診せず、私は肢体障害児になった。母のおどろき、悲しみは言うまでもない。
この姉の心の中に、ずっとひそかに弟を障害者にしてしまったという自責の念があったことを知るのは、私が成人してからのことだった。確かに意にそわない結婚をしてまでも、私の面倒をみようとした生き方からも、それは容易に想像できる。戦後の一時期疎開していた九州から母と私を呼んで、一緒に暮らしたこともあったが、若い私は姉の連れ合いとの基本的な価値観の違いに堪えられず、決断して姉の家を出た。そのときの姉の深い嘆きの言葉は、終生忘れることができない。その後離婚し、苦労多い歳月を送ってから、五〇代の姉は波乱に満ちた生涯を終えた。