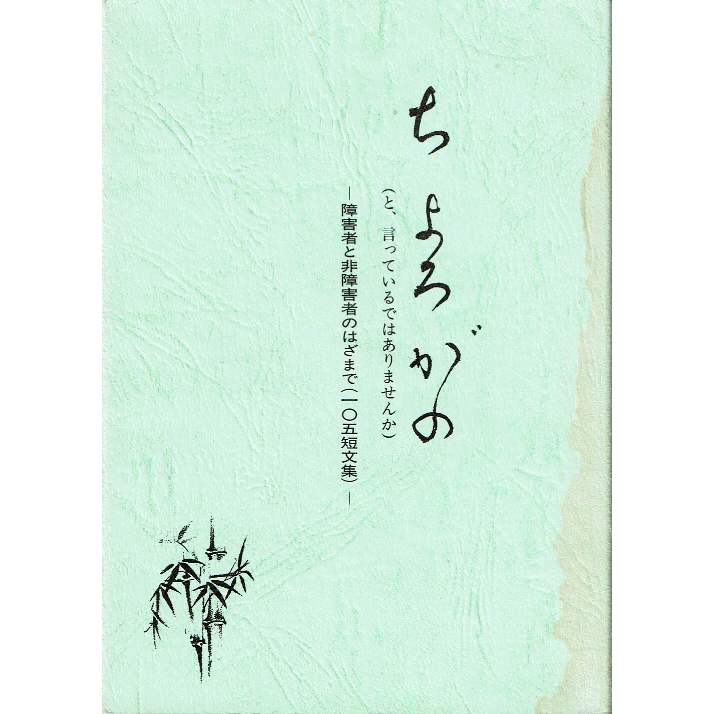あの夜のことはよくおぼえていない。ただ、梅雨どきのムシムシした暑さの夜で、ゲタを履いて懸命に夜中の道を歩いてきた額には、汗がしきりに流れていた。誰もいない踏み切り。かたわらのハダカ電球の街路灯に照らされて、線路際の夏草がやたらに茂っていた。初めは遠く、だんだんと近づき、そしてたちまち轟音と共に眼前を通りすぎた真っ黒な大きな車輪の貨物列車。強い風圧で倒れそうになりながら、辛うじて立っていたとき、またしても最後の一歩を踏み出せなかった自分の意気地なさに、歯がみする。必死に考え、決断して出てきたのに、と茫然、自失した。
一七、八歳の私。同年前後の従兄弟たちが大学受験の勉強をしたり、大学に通ったりしていることを聞くたびに、私の心は煎り豆のように跳ねたり飛んだりしていた。不安と焦りの思いが、いつもいつも私を捉えて放さない。「就学猶予」で、全く学歴を持たない者が受験できないことは分っていても、一夜にして小中の学科を通過して、皆と一緒に受験している自分を夢想したこともある。期待や希望。それらがすべて現実の前には幻想でしかないと、冷静な思いに醒めたとき、私は、将来の「自分」の存在を許せず、抹殺しようとした。しかしなお、私を越える強い「力」が私を生かして来た。