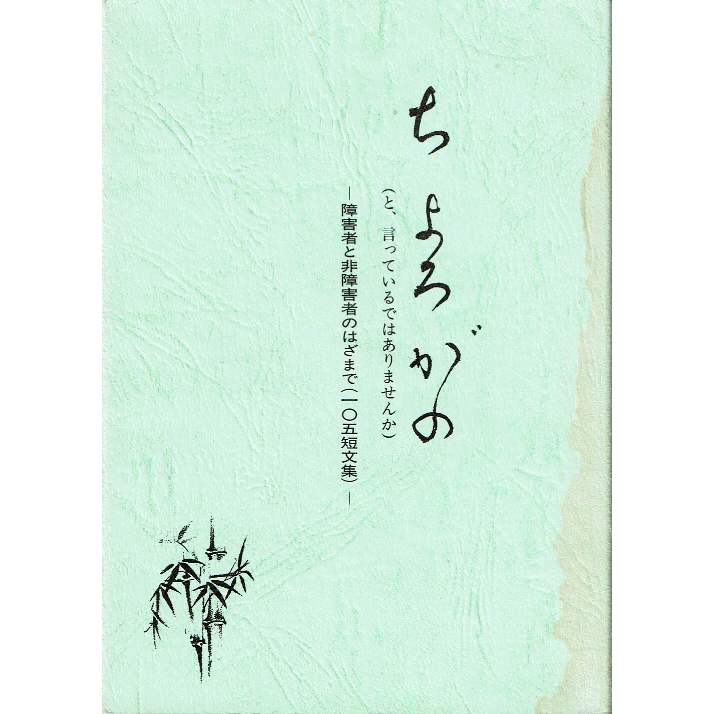一九三二年(昭和七年)は、わが家の歴史の中で、最も記憶に残る年であった。八月、住み慣れた青島(チンタオ)を離れ、大連に向う客船に乗る私たち家族には両親、四人の子どもの他、三月に五歳で亡くなった長男の小さな遺骨があった。近くの公園で子ども自転車に乗って元気に遊んでいたのが、突然、膝にバイ菌が入ったのが原因で、アッという間に、短かい命を終えてしまっていた。子どもを失った悲しみとともに、一時的にせよ、事業を成功させ、家庭を持ち、活躍した思い出多いこの港町を去るに際して、父には深い感慨があったろう。(その後、父には生涯再訪する機会はなかった)。
そして初めて移り住んだ異郷の地・大連。寒さの季節が早くくるこの都会の一隅で、わが家にはさらに過酷な月日が待っていた。十二月、女学校一年生の長女の急死。「肺炎で入院し夜中に熱が出て、苦しくて声を出すので、医者が眠らせようと注射したのが間違いではなかったのか」と、後々まで、母は涙を流しながら語っていた。毎朝、登校する前に、ごはんを食べさせてくれた姉を失い、幼い私がしばらく「アーコ、アーコ(姉の名は綾子)」と呼んで、家中を這いながら探し回っていたという。半年の辛く悲しい思い出を残し、二つの子どもの遺骨とともに、翌年の春、わが家は九州に帰った。