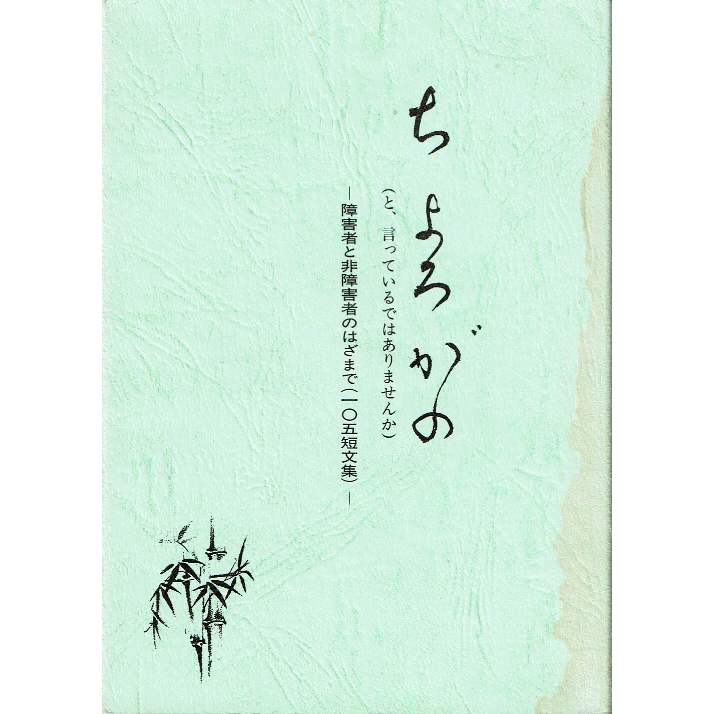いつもよく遊びに行き見慣れている谷中墓地の風景が、そのときの私にはずいぶん違った場所のように感じられた。一九四〇年の早春、朝早い時刻の墓地の木々が、濃い靄の中にボンヤリと見えた。その数ヵ月前、父が病死し三人の子どもを残された四〇代になったばかりの母は、途方に暮れていたに違いない。女学校に通う姉、小学生の妹、その中で唯一の息子の私は、肢体障害児だった。これからの生活を思いやり眠りがたい夜もあったと想像するが、ある日、未明の玄関から散歩に出かけるという母に気づき、ついてきた私だった。腰掛けた墓を囲んだ石の冷たさを覚えながら、母の着物の袖に顔を伏せている私に対して、母は別段、何も言わずにいた。しかし、その沈黙の中で、私は幼く鋭い感覚で(後にも先にも一回限りの)母の殺意を感じた。それには理由があった。時折母が呟くように娘たちに「四国の叔父さんの子どもになってくれるか」というのを聞いていた。四国の叔父とは、子どものいない大手会社の課長をしている母の最も親しい弟で、そこなら経済的に迷惑にはならないだろうと考えたと思う。それを耳にしているうちに私は動揺した。「では自分はどうなるのか」。その後の、母がどのように考え直したか、私は知らない。ただ二度とそのようなことはなかった。
母の殺意