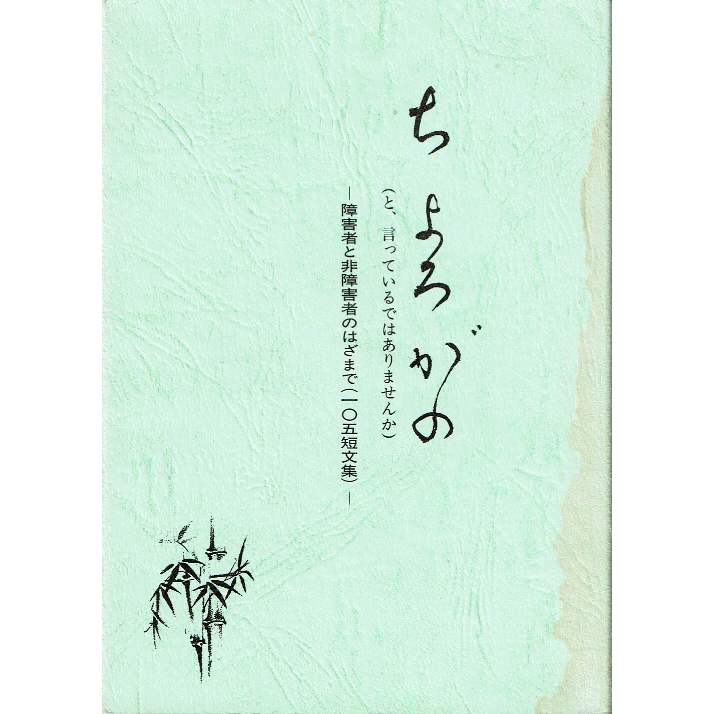父と結婚する前の母は、才気活発な元気な娘であったらしい。旧士族の次女に生まれ、質素を旨とするあまり、小作米を受け取る立場なのに「わが家は貧乏」と口癖にいう母親に反発し、終生、どんな境遇になっても、自分では「貧乏」とは決して言わなかった。「女学校に行かないなら女工だ」との厳父の一声にも、勉強嫌いを通して受験、「数学ができたので入ったのね」と合格。女学校時代のアルバムには、テニスラケットを傍らに置き、「二〇三高地」の髪形に袴、革靴の姿で友人と撮った写真が残っていた。卒業後、一時期国鉄(JR)に就職、そこでも得意の計算上手が役立った。
時々、遊びに来る若い将校の従兄弟にひそかにあこがれ、何度も縁談を断わってきた母は、十九歳のとき、父親が最も尊敬するお寺の院家(インゲ)さんから来た話には、「この話を断わったらお前は勘当する」の言葉の前に、もはや抵抗できなかった。京都・嵐山への新婚旅行の際、一番親しい弟の同伴を希望して、ようやく実現した結婚だったが、「なぜ私が遠い外地へ縁づかねばならなかったのか」との思いに母は長く苦しんだ。玄海灘を行く連絡船が、だんだん九州から遠ざかり、水平線に明りが見えなくなると、いつも「寂しくて消え入るような思いだった」と、米寿祝の席でも話していた。