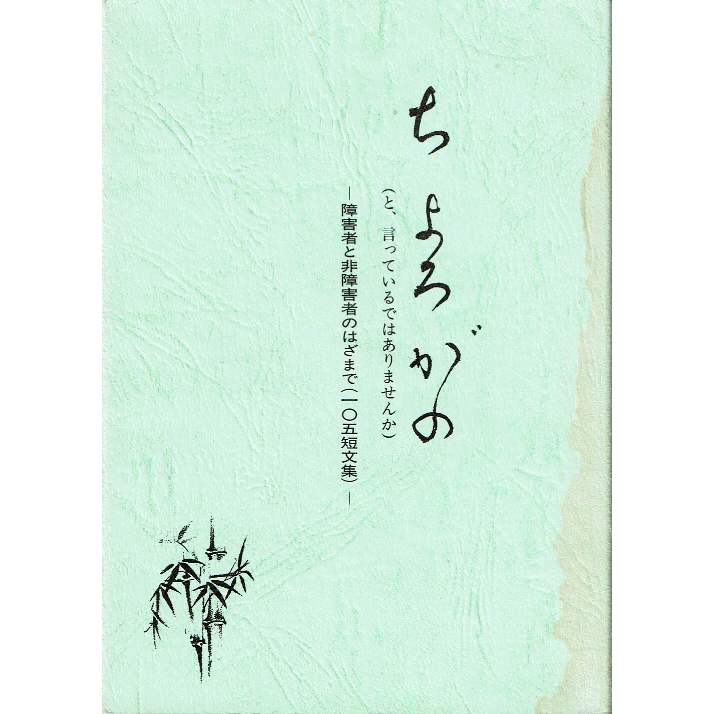息子の置いていったLPプレイヤーをかけていたら、思いがけず聞えてきたムソルグスキーの「展覧会の絵」の「古城」。この曲には、私にも遥かな若い日の思い出がある子どもの頃、家にばかりいる障害児の私のところに遊びにきてくれたのは、たいてい元気な子どもとの遊びにはぐれたおとなしい少女だった。他愛なく絵本や積木で遊んでいたが、やがて空襲に備え日本の北と南にそれぞれ疎開していった。
一〇年後、東京の姉の家に寄食していた私に会いにきてくれた昔の少女は、ブラウスの白さがまぶしい短大を目指して上京してきた若い女性になっていた。正直、二〇代の私の心は動揺した。しかし、過酷な自分の人生を次第に予想し始めていた私は「人を愛してはならない。いっそう絶望的になるから。木石のような人間になろう」と自虐的に自らを戒めていた。その後会ったとき、彼女から「この古城の曲が好き」と聞いた気がする。あれから半世紀、屈従的な姉の家での寄食生活を拒み、困難な自立への一歩を踏み出し、不安と恐れの思いを繰り返しながら、現在に至った日々を振り返ると、その心の深い動機に、あのロシア的な寂寥とした「古城」の曲があったのかも知れない。苦難と孤独の中で与えられたキリストの恵みの招きの底流にさえも。