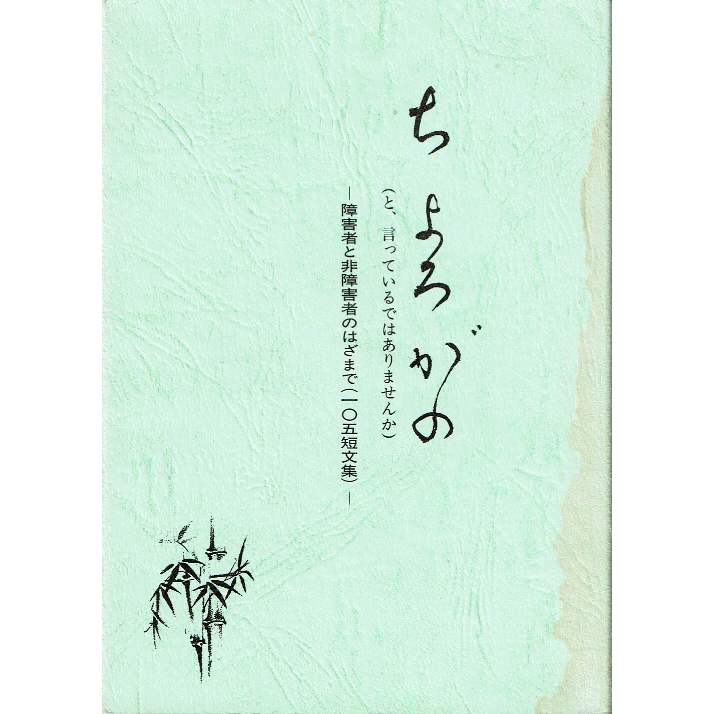父が早く死んで、戦中戦後子どもを育て上げるのに大変苦労してきた私の母が八九歳のとき、重篤な脳内出血で倒れ、寝たきりになった。高年齢でもあり、しばらくのことなら母の好きな家での介護療養がよいという妻の提案に従った。それにはどうしてもマン・パワーが必要なので、丁度大学卒業を控えた息子が、わざと卒業単位を落して留年し、手伝うという意見に(不安を覚えながらも)同意した。しかし、高度経済成長時期の金融関係を中心に、毎日届く入社勧誘書類を見もせず、ベッドのかたわらにいる彼には、正直、父親として複雑な思いだった。その状態が予想より長期間になったので、ある夜、私は決心して言った。「これまで充分にしてくれた。もういい。明日、役所で相談してくる」。すると、息子は「おやじはそんなに冷酷な人間か。自分は最期までするつもりでいる。家族の一人もちゃんとみることができなくて、世の中でどれだけ人に役立つ仕事ができると思うのか」と言った。二、三やりとりの後、結局、おばあちゃん思いの若い彼の熱意の前に沈黙したのだが、それから彼が解放されるまでに六年もかかった。その後、社会的に出遅れた彼の労苦を耳にする度に、あの夜、沈黙した自分の気弱さを恥じ、深い負い目を覚えている。
息子への負い目