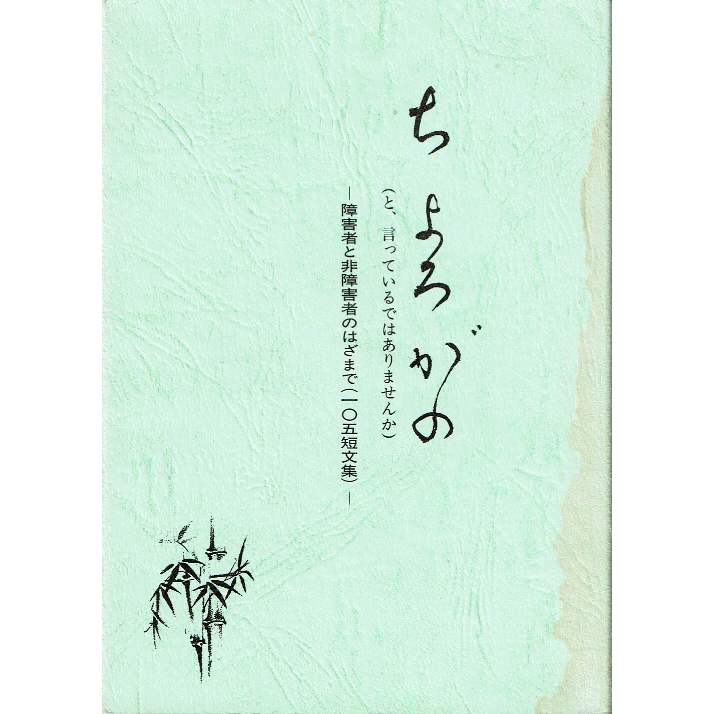一九四五年三月、本郷の千駄木で空襲に遭い、焼け出された真っ黒な私たち一家は、母の郷里九州に疎開した。現在、半日の時間で行ける所を、途中、浜松付近で米軍機の機銃掃射を浴び、神戸では車窓から前夜の大空襲の惨状を目撃、本線不通のため支線の呉線を経由、深夜の広島駅で軍部の突然の要求で強制的に全員下ろされ、やっと三日目に目的地に辿りついた。その車中、岩国を過ぎた頃、母にひとりの兵士が近づきそっと「何か食べ物はないか」と求めるのを見たとき、「神国日本、神風吹いて必ず勝つ!」と熱狂的に信じて来た若い私の勝利への信頼も、さすがに動揺した。もはや敗戦は決定的なこの状況の中でさらに五ヵ月戦い続けた結果、私たち日本人は、沖縄の地上戦闘、「神風」特攻隊(戦鑑大和も)、ヒロシマ・ナガサキの原爆、そして旧満州での難民化という深刻苛烈な悲劇的体験を歴史上に刻みつけられた。
この間、なすべき「敗戦」の決断をわが国がなしえなかったのはなぜか。私はそこに天皇制中心の「国体護持」に必死にこだわった当時の国政責任者たちの深いためらいを見る。彼らの不決断・現状認識の誤りによる絶望的な国民の惨禍を経て、漸く得た「平和憲法第九条」であることを、いま絶対に忘れてはならないと思う。