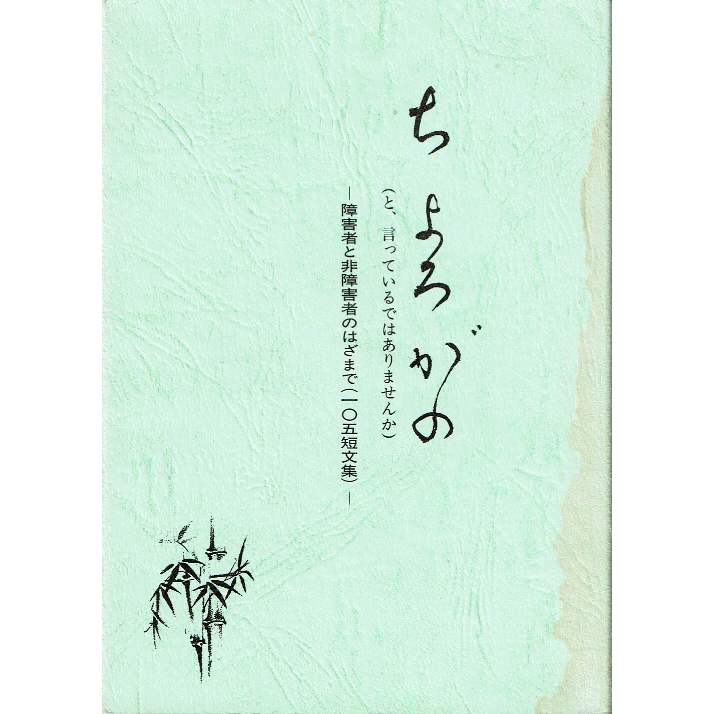ある年の年賀の返信の中に思いがけぬ寸書を読んだ。
「弟Aは昨年くも膜下出血で亡くなりました。貴方のことはよく話しており、お懐かしい方だったようで本当に有難うございました。可哀想な弟でしたので、もう一〇年も一緒に暮らしたかったとしきりに思います。」
A君と私は知り合って三〇年以上になる。時々、予告なしにやって来て、大声で勝手に話したいことを話し、又すぐ帰っていった。
出産の際の事故で、軽い知的障害を負った彼は、終生、深い愛情ある親族たちの庇護の下に生きた。身なりなどは誂えの洋服を着ていたりしていたが、両親が老いると、兄弟たちの家を転々としなければならなかった。(経済的に可能に思えたので「何か小さなお店を出してもらったらどうか」と何度か提案したが、誰も本気では取り上げなかった)
さすがに声をくもらせて「今度はどこそこに行く」と伝える彼に、私は「きっとみなさんが優しくしてくれるから、そんなに心配しなくてもいい」と何の根拠もなく言うだけだった。
最近、移された先が遠くなり、以前程には来られなくなったけれど、相変わらず大きな声で元気に暮らしていると思っていた。
A君のような者こそ、キリストの天国に招かれていると、私は信じる。